2023/10/03教養・リベラルアーツ学校生活

教科そのもののおもしろさをワオ高校の教員と一緒に探究する「本当はオモシロイ教科学習~親子で参加できる探究講座」。
今回のブログでは、9月20日に実施した音楽家の熱田先生とMC川本先生でお送りした音楽探究「熱田昭夫の音楽は哲学だ!」の様子をお届けします。
今回のテーマは、「創作意欲を喪失した作曲家ヨハネス・ブラームス」。
ブラームスは、ドイツのハンブルグ出身で、ウィーンで活躍した音楽家です。ブラームスは決して裕福な家庭ではなかったので、10歳で初めてステージに立ち、13歳からレストランなどで演奏して家計を支えていました。
全盛期は、ヨーロッパトップクラスの作曲家と高評価でしたが、一度、創作意欲を消失して早々に引退してしまいました。
今回は、そんなブラームスの生き様、哲学に迫ります。
ブラームスは、63歳にウィーンで亡くなっています。
35歳で亡くなったモーツァルトや31歳で亡くなったシューベルトなどの他の有名な作曲家と比べると、比較的長生きと言えます。彼らと同じ年代で亡くなっていたら、ブラームスが晩年に書き上げた名曲の多くが生まれなかったことになります。
そんな晩年の名曲の一つに「クラリネット・ソナタ」があります。みなさんは、この音楽を鑑賞してどのようなイメージが湧きますか?
「優雅な気持ちになる。」
「風や川の流れを感じる」
「行ったことはないけど、ヨーロッパの草原みたい」
と、イベント参加者からも感想がありました。
ブラームスは、ウィーンという大都会で生活していましたが、自然や田園風景が好きだったそうです。
この曲はブラームスが亡くなる数年前に作られたもので、目の前の風景はもちろんあるだろうけれども、思い出の中の田園風景をイメージしたものかもしれませんね。
さて、ここで問題です。
音楽家で「三大B」と言えば誰でしょうか?

答えは、ドイツ生まれの3人の偉大な作曲家「バッハ、ベートーヴェン、ブラームス」です。
熱田先生によれば、バッハは図抜けて偉大な作曲家で、その流れを汲んだ努力の作曲家が、ベートーヴェンとブラームスだそうです。もう、バッハは人間とは思えないほどだとか。
ここでもう1曲、ブラームスの音楽を紹介。
「ハンガリー舞曲第5番」というブラームスの名曲です。
ドイツ出身のブラームスが、なぜハンガリーの曲を?と思うかもしれませんが、実は1867年から1918年まで、ウィーンは「オーストリア・ハンガリー帝国」の首都でした。ハンガリーのジプシー(ロマ)音楽に触れる機会は十分にあったのです。
余談になりますが、この曲、よくCMやテレビ番組などでよく聞きませんか?
クラシックの名曲は著作権が切れている「パブリックドメイン」なので、権利関係からも利用がしやすく、CMやテレビ番組などでよく使われます。このブラームスの「ハンガリー舞曲」も、よくCMで使われていますよね。
ただ、CMなんかで、クラシックの名曲を初めて知るというのは、なんだか教養がないみたいで恥ずかしい気もします。そもそも、クラシックを聴く機会があまりない方のほうが多いのではないでしょうか。
そこで、熱田先生からこのようなアドバイスが。
その音楽に興味を持つことができたのなら、入り口はなんでも構わない。知るきっかけがどういったものであれ、魅力に気づくことが大切と。
最後にブラームスの作品の中でも評価が高い、交響曲「交響曲第1番」。
この作品は、ブラームスが43歳の時のものですが、実は、完成するまでに21年もかかっています。
では、なぜ21年もかかったのでしょうか?
偉大な作曲家「三大B」でもお伝えしたように、ブラームスより以前に有名だったのが、ベートーヴェンです。
ベートーヴェンは9曲の交響曲を作曲しましたが、いずれも名曲ばかり。それらがあまりにも素晴らしいので、ブラームスは生半可な曲はかけないというプレッシャーがあり、完成までに21年もかかったのではないか、と言われています。
それだけ、ブラームスが苦労して作り上げた「交響曲第1番」。
現在では好きな交響曲のランキングを作るとまず間違いなく上位に入るとか。ベートーヴェンの第9と並んで、良く演奏される交響曲でもあります。
また、このような高評価を得る理由の一つが、この時代の音楽が、形式を重視する「古典派」から、感情を重視する音楽「ロマン派」へと移り変わったからだと言われています。
ベートーヴェンの「ロマン派」の交響曲を受けつくと評価されたブラームスですが、56歳の時に突如として遺書を書き、活動休止してしまいます。
ここにも、彼が尊敬するベートーヴェンの影が見えると言います。
実は、ベートーヴェンは56歳で亡くなっています。ベートーヴェンがその時に到達していた高みと、現在の自分を比較して、彼我の差に絶望し、音楽家として終わりにしようと考えたのではないか、哲学的に自分自身を「懐疑」した結果ではないか、いうのが熱田先生の考えです。
さて、音楽家としての「遺書」を残して引退したブラームスですが、2年後には活動を再開しました。それはもちろん、作曲がしたくなり、再開したのですが、なぜ、新しい曲を書く気になったのでしょうか。
それは、ブラームスより23歳年下のリヒャルト・ミュールフェルトという、当時世界一とも評価されるクラリネット奏者の演奏を聞いたことでした。

ブラームスは、ミュールフェルトの演奏に強い感銘を受け、友人であるピアノ奏者クララ・シューマン(作曲家ロベルト・シューマンの妻)に、その驚異的な演奏について「man kann nicht schöner Klarinette blasen als es der hiesige Herr Mühlfeldtut.(当地のミュールフェルト以上に美しいクラリネットを吹くことは誰にもできません)」と、書き送っているほどです。
そんなミュールフェルトに自分の曲を演奏して欲しいと思い、作曲を再開したそうです。
なぜ、ブラームスは、ミュールフェルトに自分の曲を演奏してほしいと思ったのでしょうか?そこにはどんな思いがあったのでしょうか?
「素晴らしい奏者の力で、新しい自分の扉を開けてもらえる気がした」
「自分の曲を普通の演奏者よりも自分よりも深く表現して演奏して欲しかった」
と、イベント参加者から回答がありました。
この回答に、熱田先生は驚きました。作曲家が気づかない曲の魅力を、指揮者や演奏者が引き出すことは実際にあるのだそうです。
熱田先生が考えるブラームスの思いは、「プロフェッショナルからアマチュア精神への回帰」だそうです。
つまり、お金を稼ぐ仕事としての音楽ではなく、利害から離れて、純粋に向き合う音楽として、本当に自分の書きたい、演奏してもらいたい、聞きたい音楽だけを書きたくなった、ということ。
作曲活動を再開したブラームスは、その年のうちに、ミュールフェルトのために「クラリネット三重奏曲 イ短調(作品114)」と「クラリネット五重奏曲 ロ短調(作品115)」を書き上げています。最初に聞きました、「クラリネット・ソナタ」(作品120-1、120-2の2曲)はその後に書かれたものです。
熱田先生は、このブラームス最晩年のクラリネット曲4曲について、次のようにおっしゃいました。
この4曲は完璧な曲。ベートーヴェンの曲を吹いていても、作曲家の悩みや苦労や推敲が感じられることがあるが、ブラームスの4曲には全く迷いが感じられない。本当に書きたいものだけを書いたアマチュア精神の成せる業ではないか。
しっかりと音楽の研究し、実力をつけてプロとして極めて、そのうえで少し時間をおいて冷却したからこそ、無欲のアマチュア精神の戻れたのではないか。
だからこそ、プロフェッショナルな能力とアマチュア精神のいいところが掛け合わさり名作が生まれたのではないだろうか。
今回ご紹介した音楽を、是非、もう一度、聴いてみてください。
みなさんは、どのようなイメージや感情が湧きますか?
▼今回ご紹介したイベント情報はコチラ▼
ワオ!な先生による本当はオモシロイ教科学習 親子で参加できる探究講座
毎週水曜日 18:00~19:00(オンライン)
2023/10/03教養・リベラルアーツ学校生活
その他の記事
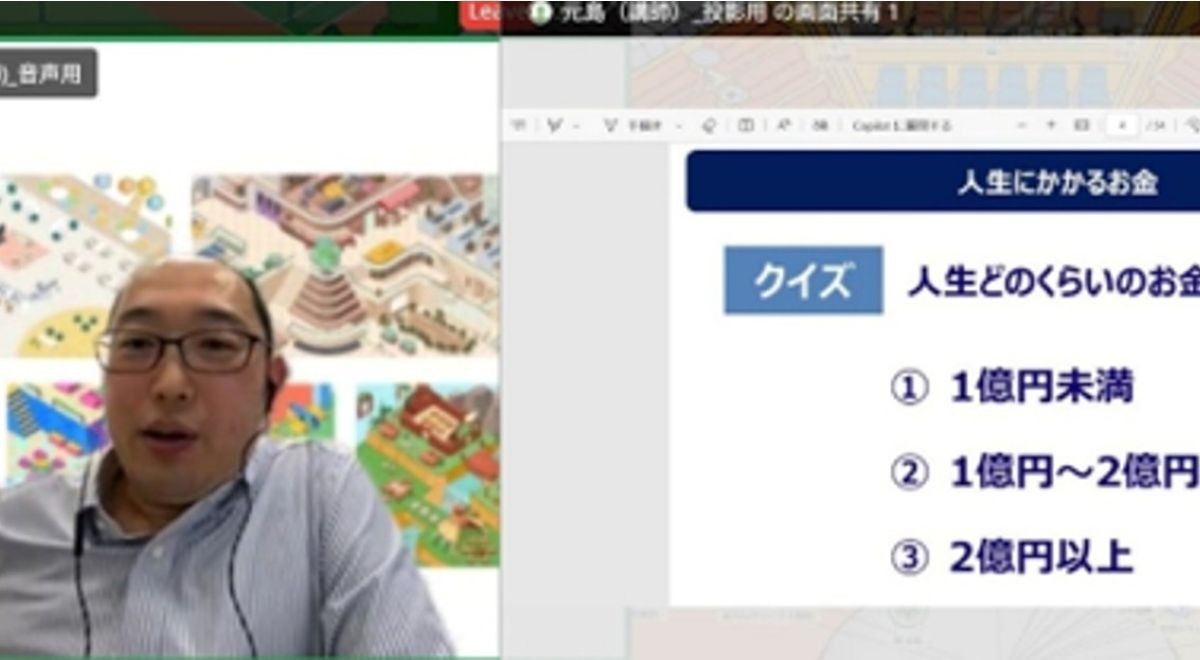
人生とお金を考える一歩に みずほフィナンシャルグループによる金融教育
2026/02/03

【岡山キャンパス】岡山県立美術館で対話型鑑賞をしました
2026/01/30

【特別活動】「毎日朝起きるのが楽しくて仕方ない」―Pebble株式会社様による講演会を開催!
2026/01/29